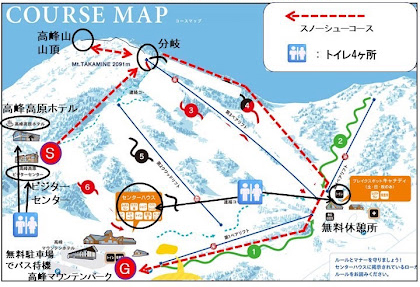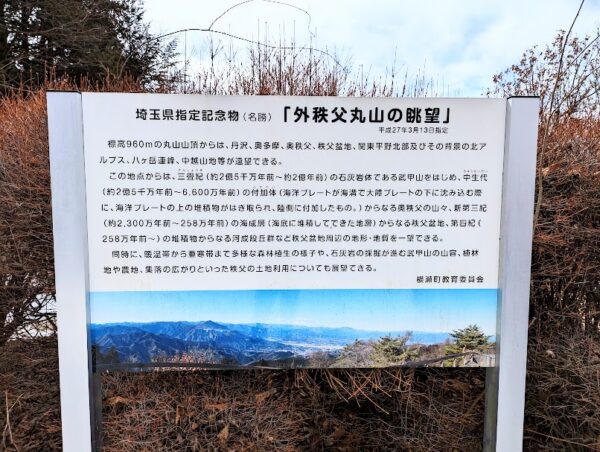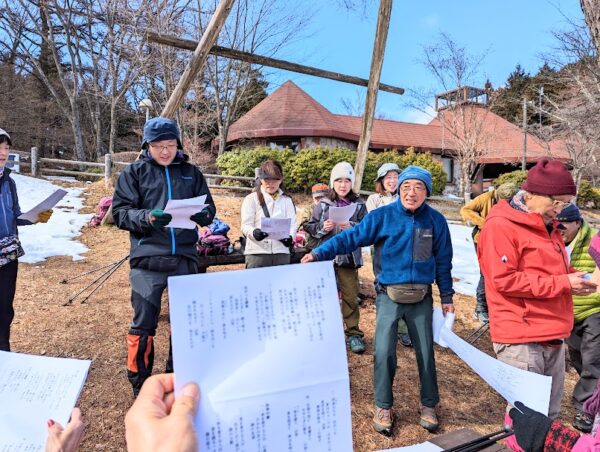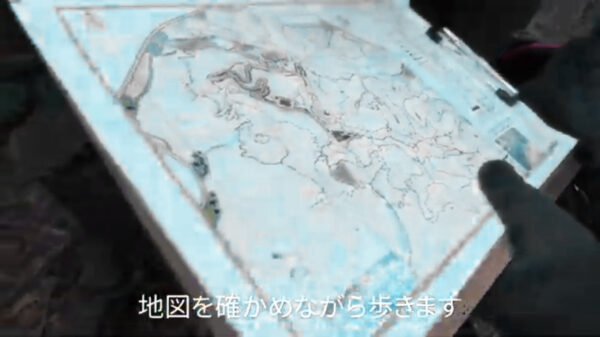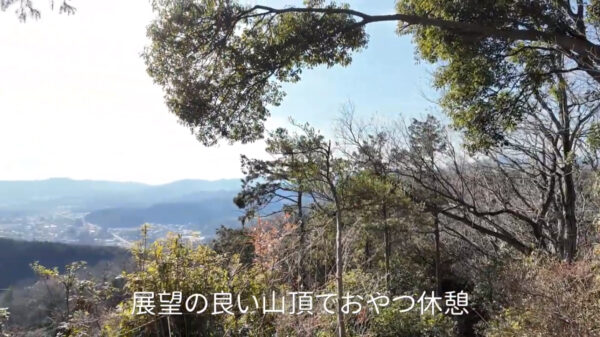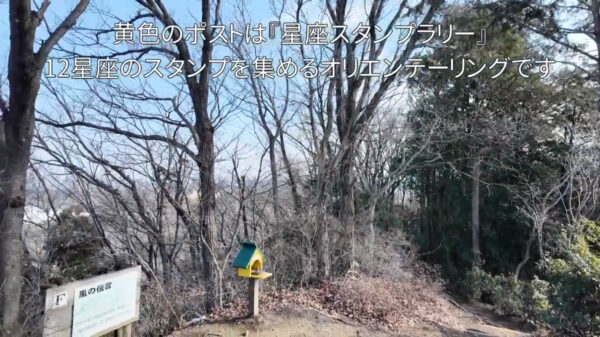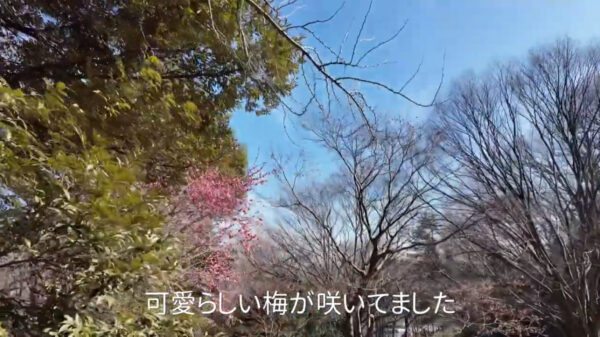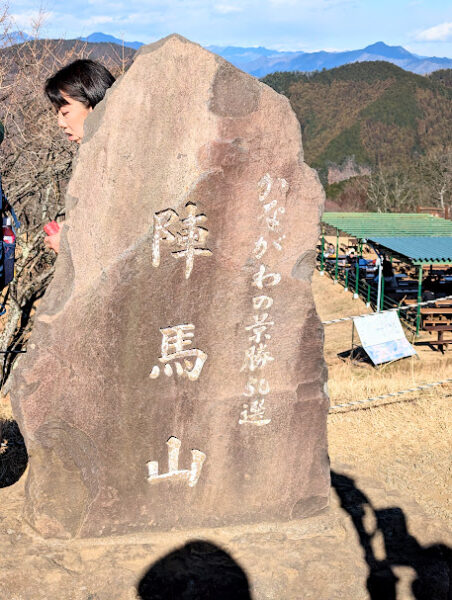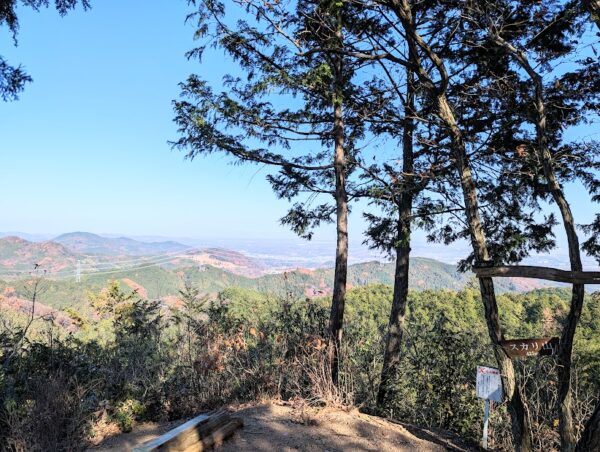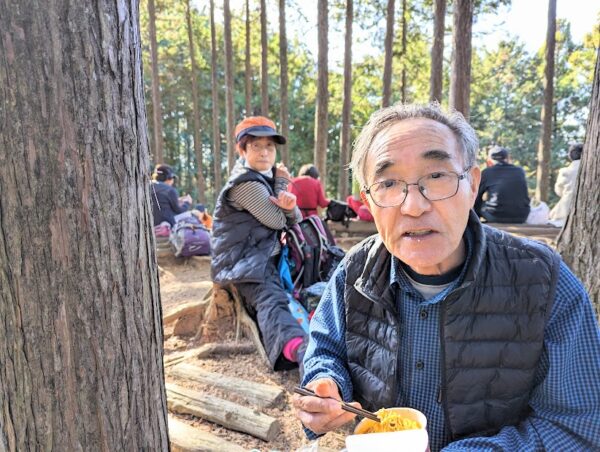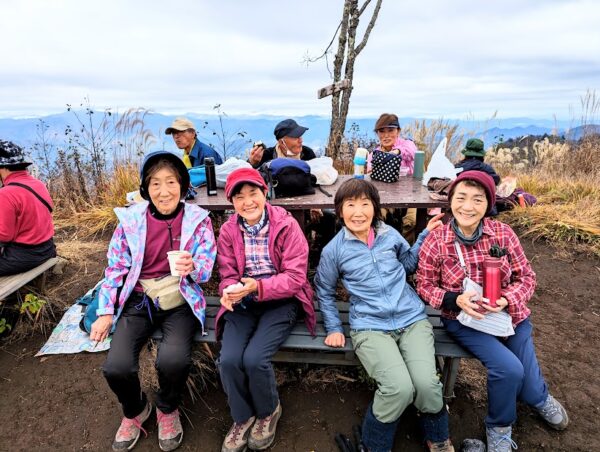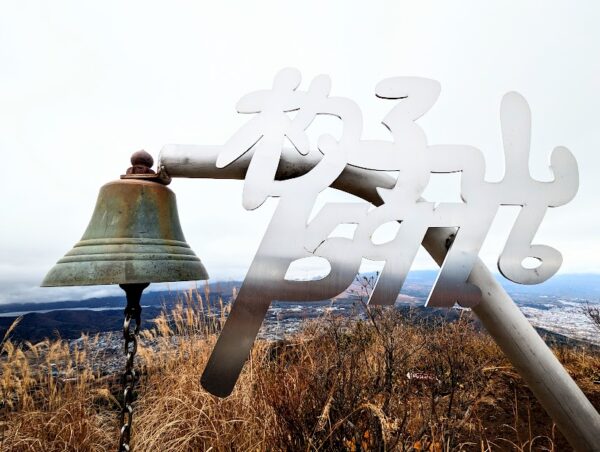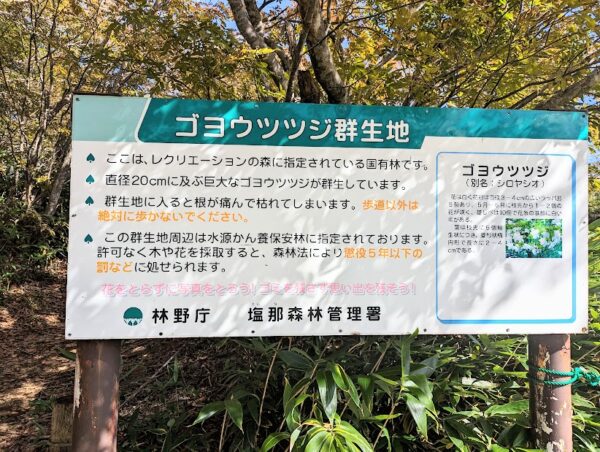今月の「峠山の会」定例山行は、栃木県日光市の鳴虫山(なきむしやま)。
鳴虫山は、日光駅からのアクセスも良く、季節ごとに表情を変える自然が魅力の標高1103.5mの山。
「この山に雲がかかると雨になる」と言われていたことから鳴虫山と名付けられたのだとか。
下見で訪れた際には、登山道が荒れて歩くのが大変な箇所もあったのですが、
さあ、今回はどういった感じでしょうか。
ルートは、神ノ主山(こうのすやま)、鳴虫山、合峰(がっぽう)、独標(どっぴょう)と縦走し、憾満ケ淵(かんまんがふち)に降りる周回コースです。
まずは電車を乗り継いで東武日光駅に到着。
登山道中にはトイレが無いので駅で用を済ませます。
駅前の大通りを歩き、登山口の方へと進みます。
朝からすっきりとしたお天気で幸先が良さそうです。
道路の先には日光の連山が迫って見えます。
高山になるとまだ少し雪も残っているんですね。

御幸町(ごこうまち)の橋を渡ったところで準備体操。
この日、体操をリードしてくれたのはT瀬さん。
初の仕切り役でしたが、頼もしかったです!

こちらが登山口。
最初はやや急登で始まります。

しばらく進んだ所で衣服調整をして、さらに登って行きます。

辺りには小さなスミレが咲いていました。

会員の方々はみなさん、健脚揃い。
列を乱さず、等間隔で進んで行きます。
快晴なので、物凄く暑くなりそうな予感がしてきます。

針葉樹林に入るとひんやりとした風がそよいでいて、
程良いクールダウンになりました。
春の登山ならではの爽やかな心地良さを実感できましたよ。

所々根っこがむき出しになって道を遮っています。
根に引っかからないように、足を踏ん張ってまたいで行きます。

序盤はずっとくねくねの登山道をゆっくり上がって行く感じです。

20~30分を目安として程よい箇所で小休憩。
水分やエネルギーを補給します。

地面には桜の花びらが散っていましたが、
頭上を見上げると、空高く伸びた山桜の枝にはまだ少し花が残っています。


登山口から45分くらいで神主山に到着。
進み具合は順調そのものです。



南側斜面にはアカヤシオが咲いています。
樹高の高いツツジなので、花は遠くに咲いている感じ。
地味ながらも爽やかに春を感じさせる薄ピンクの花です。

木の根が階段状に張巡らされた箇所が続きます。
少し行っては上ったり降りたりのアップダウンが繰り返すので、
なかなか登り甲斐のある登山道です。


方々にカタクリの花が咲いていました。
ちょうどカタクリの開花時期になっていたようです。
カタクリは早春、雪解けの時期に山林の北斜面で花を咲かせ、
その花びらは朝日を受けて広がり、夕方には閉じるのだそう。
少しピンク味がかった紫の花色も素敵ですし、
華奢な風貌と斑の入った葉も魅力的ですね。



山頂手前の上り坂を一気に登ると鳴虫山の頂上です。
標識を囲んで集合写真。
今回参加のメンバーは17名。



昼食は30分以上時間を取って、しばしの間ゆっくり過ごします。
暖かいので気分も最高です。





山々の眺望は木々が遮ってしまい少し残念ですが、
その分ツツジの花が賑やかになっていたので良かったです。

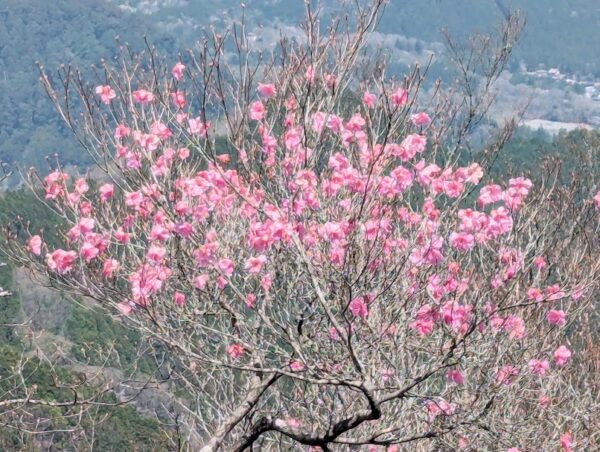

ランチ後は下山。
急坂、木の階段から始まります。
階段の手摺はもろくなりかけていました。

根っこや岩がごろごろしているので、
滑らないように注意しながら降りて行きます。
なるべく間隔を1m以上開けるように心がけ、
両手にストックはむしろ危険なので、片側ストックで進みます。


下りといってもいくつかピークがありますので、
上ったり降りたりします。
そして合峰に到着。
下りも順調に歩を進めています。


岩場の段差あり。
ロープの張られている箇所もちょくちょく現れてきます。



それにしてもみなさん、さすがですよね。
ペース良く難関をクリアしていきます。





独標に到着。こちらが最後のピークですね。


ですがまだまだ難関は続きます。

今ルート一番の難所がこちら。
根っこの下にあるはずの土ががえぐられて、急斜面の途中で根が道を阻んでいます。
根に乗ってまたがないと進めないのですが、その位置がそこそこ高いので、
足元が地面に付かないまま乗り越えなくてはなりません。
相当たいへんなのですが、こういった箇所を進むのが楽しいともいえますよね。






ここまで来れば、もうあと少しです。

ミツマタの群生地に到着。
ちょうどミツマタも満開を迎えていました。



そして終点ともいえる憾満ケ淵に到着。
並び地蔵(化け地蔵)と渓流・滝が見どころの観光スポット。


この後は安川町バス停からバスに乗り、東武日光駅に戻りました。
こんな感じで今回の山行はおしまい。
無事下山できてひと安心です。
それも予定より早めの終了になりました。めでたし、めでたしです。
みなさま、お疲れさまでございました。
PS.朝霞台でのお疲れ会の様子。
飲んで食べて大満足の1日でしたよ!


つっちーさんのブログ
つっちーの日々
【鳴虫山】アカヤシオとカタクリの咲く山
**********
※「峠山の会」では常時、会員を募集しています。
埼玉県富士見市界隈にお住まいの方で登山に興味のある方、
私たちと一緒に登山を楽しみませんか?
是非とも、ご参加をお待ちしています。
「参加希望」などと件名を付けてお問い合わせください!!
お問い合わせはコチラから → お問い合わせ
ただし、会員になられるには月1回の定例会にお越しいただいて、
会費をお支払いいただくことが必要です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。 → 会員募集案内
**********
ホーム
とうげやまブログ
動画~YouTubeチャンネル
会員募集案内
定例山行予定
定例山行の記録
過去の定例山行
過去の山行の様子
会員のページ1
会員のページ2
県連 高橋さんのページ
リンク
お問い合わせ
QRコード
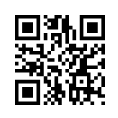
※ スマートフォンから上のQRコードを読み取ると、とうげやまブログのページをご覧いただくことができます。